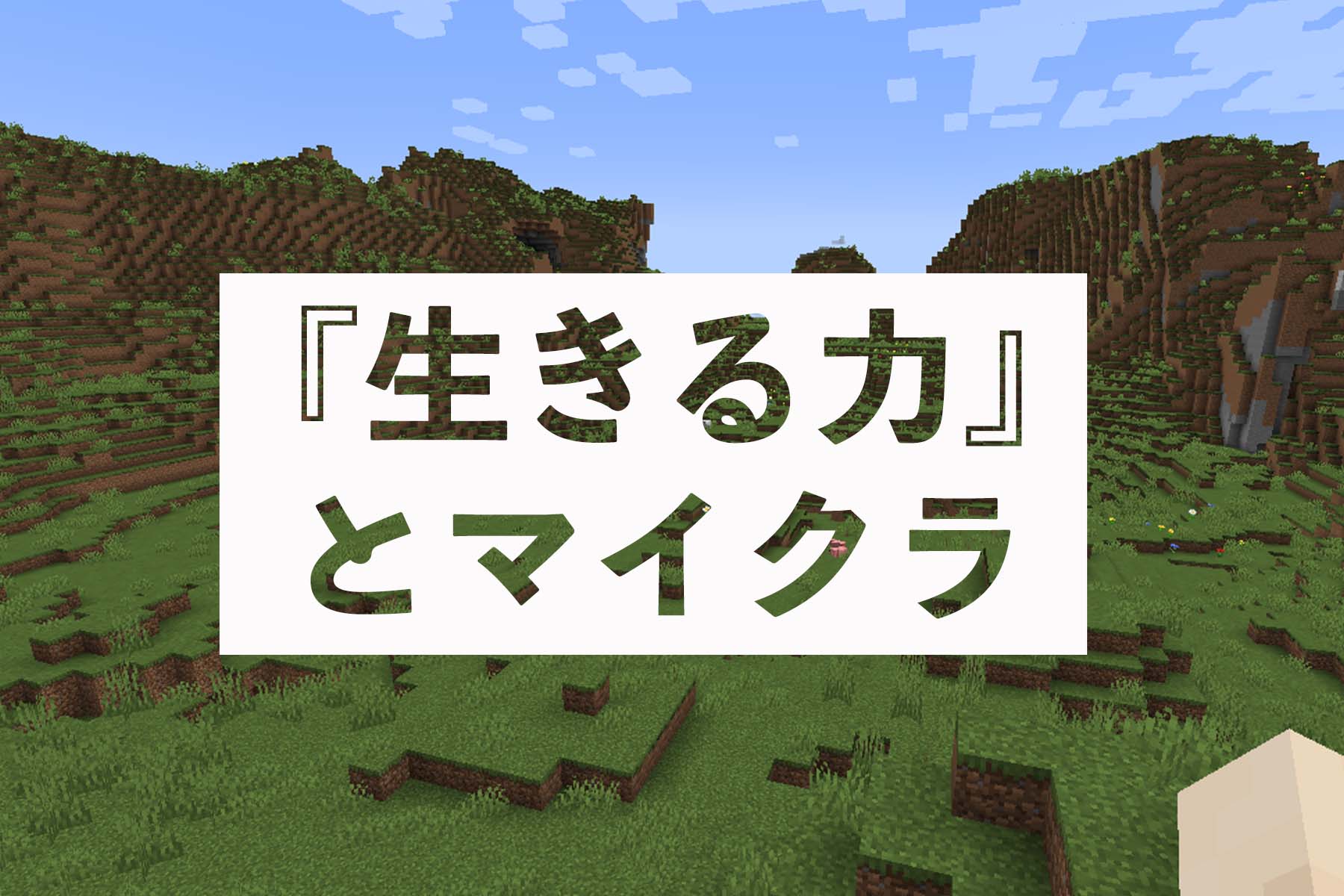マインクラフトと学び|期待できる教育効果6つ
マイクラと学び
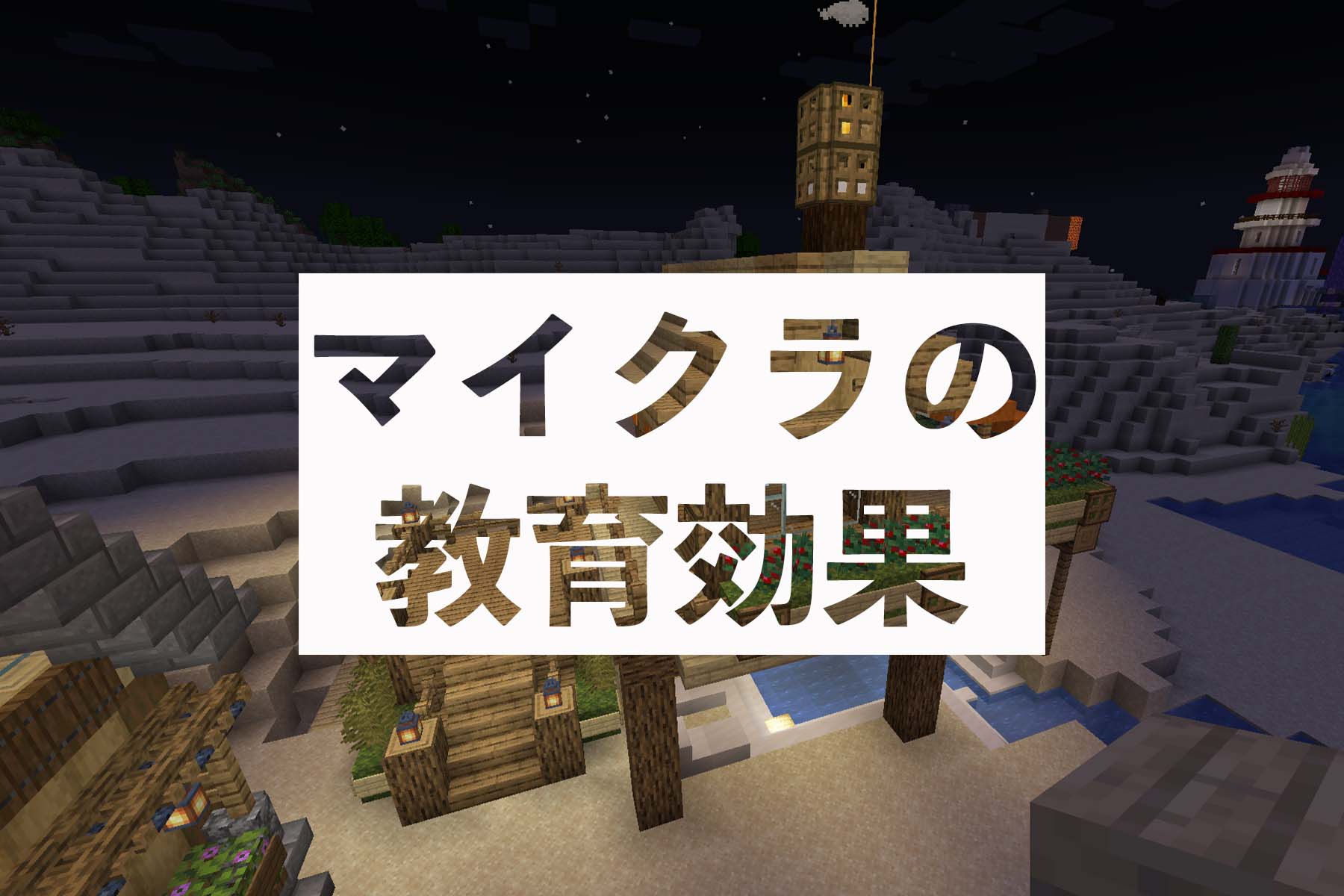
子ども達の間で爆発的な人気を集めるマインクラフト、通称マイクラ。
教育面で良いと聞くことも多いですよね。
しかし、具体的に何が良いのでしょう?
この記事では、マイクラが学習現場で活用されている事例を読んで見えてきた、マイクラの教育効果6つをご紹介します。
目次
マインクラフトに期待できる6つの教育効果
マイクラの教育効果を調べるため、学校でマイクラを活用した事例をいくつか読んでいきました。
そして、その中でも教育効果があるとして特に支持を集めていた6項目を以下に挙げました。
- 創造性
- 表現力
- 問題解決能力
- 協働性
- 計算力と計画性
- ICTスキル
新しいものを作り出す『創造性』
マイクラは、ブロックで構成された世界で、自由にモノづくりを楽しむことができるゲームです。
デジタル版のLEGOのような感覚で遊べ、しかも部屋の広さなどの物理的な制約を受けることなく作りたいものを表現できる環境は、子どもたちの創造力を育んでくれます。
あるカナダの学校でのマイクラを取り入れた授業の調査では、生徒さんから
『無限にアイデアを試せる!』
『なんでも作ったり組み合わせたりできる。発明者になった気分』
『作ることが大好き。自分は作るのが得意だと思う』
といったコメントが聞かれ、どの子も創造することに夢中になっている様子が窺えました。
自分の考えを相手に伝える『表現力』
自分のアイデアが形になったら、次はそれを共有したくなりますよね。
子ども達は、自分の作品や制作状況を周りに説明する中で表現力を養うことができます。
我が家でも『見て〜!』と子どもが見せにきて、分かりにくいところを質問をすれば、手を替え品を替え話してくれます。
そうした会話や発表の機会を通して、相手へ分かりやすく伝える表現力が育ちます。
また、アイデアを形にし、理解を得るという経験を繰り返すことで、自己達成感の向上にもつながったという指摘もありました。
問題を見極めて解決する『問題解決能力』
マイクラのサバイバルモードでは、プレイヤーは生き残るために直面する様々な問題を解決しなければなりません。
例えば、敵に対する戦闘、空腹を満たす、資源の調達など…これらを克服するために探検しながら道具、家、食糧などを自前で調達していきます。
まさにサバイバル。
自分で何を解決すべきか考え、実践しながら問題を解決していく必要があり、問題解決能力が育まれます。
現実世界では難しいことでも、何度でも失敗でき、すぐにやり直せる点も、ゲームならではの魅力です。
他者と一緒に目標を達成できる『協働性』
学校で利用された例では、協働性の促進も際立った効果として挙げられていました。
マインクラフトは、多人数でプレイできるゲームであり、プレイヤー同士のコミュニケーションとコラボレーションが重要な役割を担います。
マイクラを導入した授業では、子どもたち同士で一緒にものを作ったり、情報やスキルを共有したり、役割分担をしたりと、自然に協働姿勢が形成される様子がよくみられていました。
前出のカナダの学校の生徒さんの多くも
『分からないことは友達に聞いて解決できた』
『チームの一員として作業するとはどんなことか学べた』
『チームで作業するのって楽しい!』
というコメントを残していて、自然に協働姿勢が生まれていることが窺えました。
プロジェクトを進めるために必要な『計算力と計画性』
マイクラで遊んでいると計算や計画が必要な場面が繰り返し訪れます。例えば以下のような場面では、先を見越した計算や計画ができることがゲームを進める上で有利になってきます。
- 数を数えながら必要な個数分のブロックを置く。
- 必要な数の道具を用意するために、素材ブロックがいくつ必要か計算して素材を集める。
- 建築物の図面を書いて、建築計画を立て、必要なブロック数を見積る。
- 入試して手元に持ちきれないブロックや食材をわかりやすく保管する。
- 決められたゲーム時間内に何をどこまで作るか目標を立てて実行する。
こうした場面が何回も訪れるので、マイクラで遊んでいるうちに、計算力や計画性の向上が期待できます。
今の時代に求められる『ICTスキル』
マイクラで遊ぶ中で、これからの時代を生きる上で欠かせないICTスキルとの付き合い方を学んだという意見も多かったです。
マイクラの攻略法や建築案はウェブ上でたくさんの情報を見つけることができますので、欲しい情報を検索し、吟味し、利用していくことで情報収集・活用能力が養われます。
また、マイクラではコマンドを使った操作ができます。
大量のブロックを並べるといった面倒な作業が、コマンド一発でできると実感できるのは、プログラミングへ興味を持つ上では効果的な第一歩です。
さらに、追加アプリを入れたり教育版マインクラフトを使えば本格的にプログラムを書いて遊ぶことも可能で、様々な面でICTスキルを養うことができます。

ゲームの枠を超えた学習ツールとして世界中で活用されているマイクラは、調べてみると様々なプラスの効果が挙げられていました。
その中でも、マイクラが成長につながった理由として多く挙げられていたのが、上記の6項目でした。
こうして並べてみると、ここに含まれる創造性、問題解決能力や表現力、協調性、ICTスキルなどはこれからの時代を生きる子どもたちに必要とされている力と重なります。
文部科学省の新学習指導要領では、育むべき子どもたちの「生きる力」を以下のように説明しています。
現在、私たちを取り巻く社会経済のあらゆる面が大きく変化しており、知識が社会・経済の発展の源泉となる「知識基盤社会」が本格的に到来しようとしています。…「知識基盤社会」では、幅広い知識と柔軟な思考力に基づく新しい知や価値を創造する能力が求められるようになります。 これからの社会を生きる子どもたちは、自ら課題を発見し解決する力、コミュニケーション能力、物事を多様な観点から考察する力(クリティカル・シンキング)、様々な情報を取捨選択できる力などが求められると考えられます。
マイクラの教育効果、それは、子どもたちがこれからの社会で生きていくために必要な能力と親和性が高いと言えそうです。
まとめ
この記事ではマイクラに期待できる教育効果をまとめました。
ここで紹介した創造性、表現力、問題解決能力、協働性、計算力・計画性、ICTスキルは、マイクラの学びの効果として、特に良く挙げられていた項目でした。
これらは、直接的に教科科目につながる訳ではないものの、今の時代を生きるために育むべき能力と言われているものと重なります。
ここでは主に学校での利用例を参考にしてきましたが、家庭内やお友達と遊ぶ中でも同様の効果が期待できるでしょう。
『楽しく遊びつつ、子どもの将来にとって何かの力になるゲームがいいな』という場合、マイクラは是非ともお勧めです。
その際には、ぜひ周りの大人も一緒に楽しみつつ、ここぞという時には適切な働きかけや助け舟を出してあげられるとより良いと思います。
私自身も、育児や仕事の中で遊びと学びがじんわりつながる手助けをしていければいいなと思います。
参考
- Karsenti, T., Bugmann, J, and Gros, P. P. (2017) Transforming Education with Minecraft? Results ofan exploratory study conducted with 118 elementary-school students. Montréal : CRIFPE.
- How Wales Hwb created a national professional development program with Minecraft - Minecraft Education
- Creative Learning and Leadership | Minecraft: Education Edition at India’s Sat Paul Mittal School - Minecraft Education
- タツナミシュウイチさんインタビュー前編!「マインクラフト」が子どもの生きる力を育てていく~魅力を徹底紹介!~ - ユリイカのタネ
- 「教育版マインクラフト」第一人者にインタビュー(後編) 〜「マイクラ」で観光ガイド!学校での実践例〜 - コエテコ
- “好き”と“楽しい”は学びに向かう原動力、マイクラカップ大賞受賞校に聞く教育版マインクラフトで培われた力とは――Minecraft カップ 2019 全国大会 大賞受賞・加藤学園暁秀初等学校インタビュー - Watch Headline
- 新学習指導要領保護者用パンフレット - 文部科学省